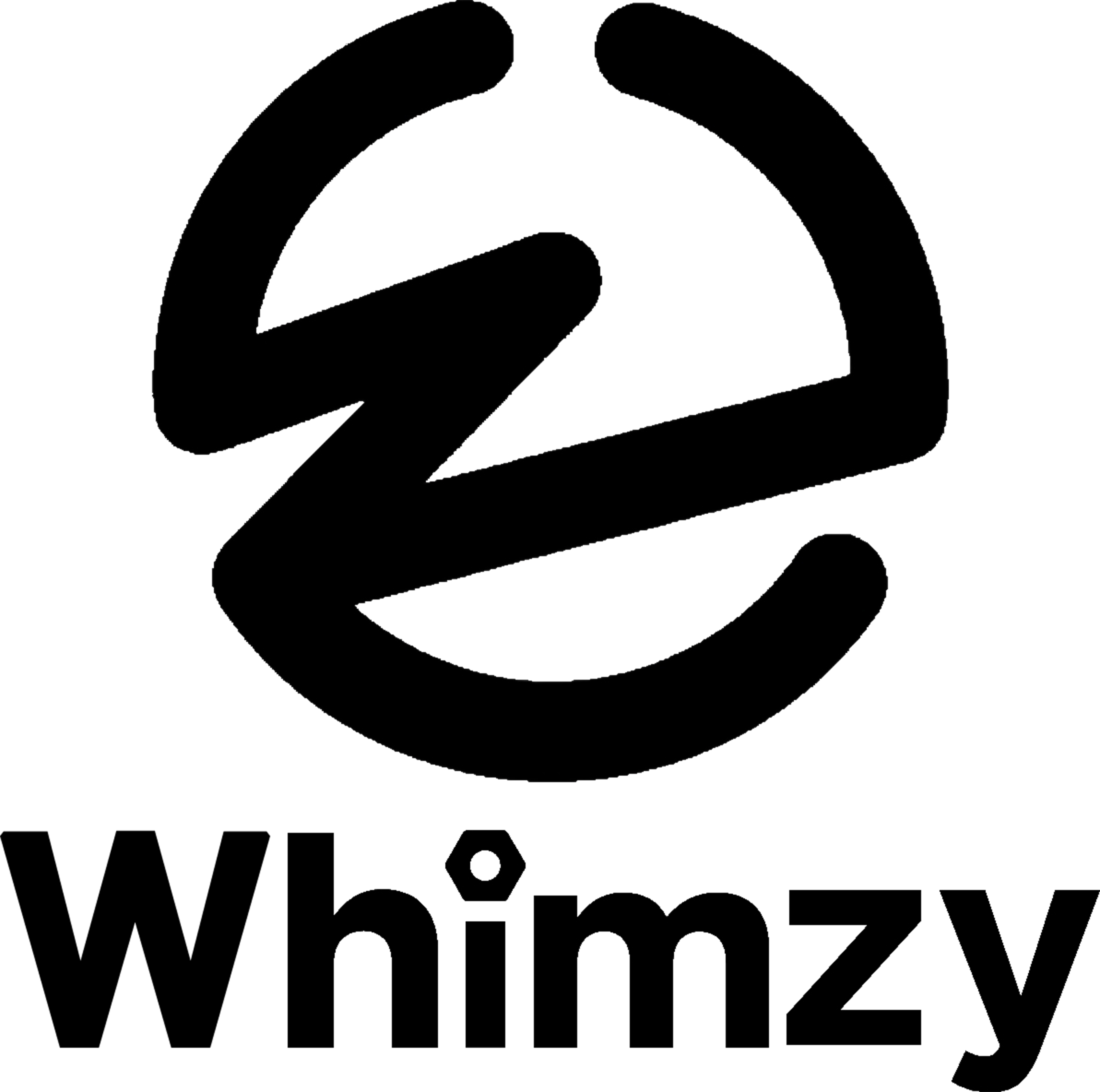2023/12/01 17:06
二次燃焼焚き火台 開発から商品化までのお話 Vol.3 今回は商品開発に至るまでに発生した問題や課題、そのプロセス、また今後の展望について開発者の大澤へのインタビューをしてまいりましたので、是非ご覧ください。 ・薪の取り出し方問題 二次燃焼の綺麗な炎を発生させながら高火力で炭を作る焚き火台、ということを基本コンセプトに考えて、設計・試作をしていく中で問題となったのは、炭の取り出し方です。 最初のプロトタイプなんかは、出来た炭を取り出すことは出来ても、危険な状態で取り出す状況となってしまいました。また本体のサイズを小さくすると、取り出せる炭の量は減ってしまうし、取り出しにくさに繋がってしまこともわかりました。 そこで、いかに綺麗に簡単に取り出せるか、ということがその後の課題として見えてきました。 安全性を考慮しながら利便性も追求することを考え、設計をしていきました。 火ばさみで一個一個を取って移動させるのも面倒だし、時間がかかるために炭の移動を開始してから、最後のほうは灰になってしまって、使い物にならない。そうすると料理するにも時間がかかってしまう。そうなると出来た炭を一発で料理をする場所、BBQコンロなどに移動させることができる方法となります。 現状モデルでは炭受けが引き出せる構造にすることで、炭の移動が出来るようにしておりますが、移動時の安全性をもっと確保できないかと現在も憂慮しております。 ・製品化に至るまでの工程 商品化に至るまでには、プロトタイプを3台製造しています。その都度問題点・課題を見つけ、設計から製造までを見直していきました。 プロトタイプ1号機 こちらに関しては、炎に関しては綺麗な二次燃焼も発生し、炎を楽しむという面では満足できる部分はあったのですが、炭の取り出しが非常にしにくい構造でした。 サイズも一番小さいモデルではあったので、実はソロキャンパーの娘は、自分がもし持っていくならこれ、ということも言っておりました。 プロトタイプ2号機 1号機の炭の取り出しにくさを解消すべく、サイズも少し大きくして、ロストルを取り出せるような構造体へ設計変更を行いました。 しかし実際に試験を行ってみると、高温による歪みによってロストルが安全に取り出すことが出来なくなってしまいました。取り出すことは出来ても安全性に欠けることとなってしまうので、再度この点が課題となりました。 また燃焼については、1号機はロストル部から壁内への吸気を行うための通気口を設けていたのですが、外部からの酸素の流入を増やすためにこちらをふさぎ、外部からの空気の取り込口を大きくしました。また壁内の厚みをより厚くし、二次燃焼口の数も減らすことで、壁内の密度を上げ勢いよく二次燃焼が発生するようにと考えたのですが、結果として1号機に比べて炎が不安定になってしまいました。 プロトタイプ3号機 3号機は炭の取り出しやすさを最優先事項として、構造を変更。ロストル部をスライド式で取り出しが可能な構造としました。こうすることで、炭を一度に取り出すことが可能とはなりました。 二次燃焼に関わる部分については、2号機と同じ構造としました。炎のことだけを考えると1号機が一番安定していたが、酸素の取り込みを考えるとあくまで外部のみのほうが二次燃焼は発生しやすいと考えました。どこに差があるのかを考えると、壁内の温度に差があるのはないかと考えていました。ただ、2号機に比べ安定性はロストル部の設計変更によるもので安定はしてきました。 当初の目標は最低限クリアしたことで、こちらをベースに商品化することとなりました。 ・今後の展望 商品化には至りましたが、まだまだ製品としては個人的には納得がいっていない部分があるので、今後もより良い商品としてお客様にお届けできるように改良はしていく予定です。 具体的には、炭の取り出し部分の改良。こちらはまだ使い勝手、安全性の部分で改良の余地は多く残っていると感じております。自らが使う立場になって考えてみて、こうだったら良いのという案は出ているのですが、まだ実用できるレベルには至っておりませんが、引き続き検証してまいります。 もうひとつは二次燃焼の安定化。こちらも使用環境にもよってしまう部分がもちろんあるのだけれども、より安定して二次燃焼が発生するように改良はしていきます。 プロトタイプでの検証を踏まえて、壁内の空気層の厚みの調整によって温度を上げることが出来ないかを考えています。 現状の商品でも今までには無いコンセプトの商品ではありますので、使用していただくお客様には満足いただけるとは考えておりますが、引き続き改良をしてまいりますので、次期の製品にもご期待いただければと思います。 今回は商品開発に至るまでに発生した問題や課題、そのプロセス、また今後の展望について開発者の大澤へのインタビューをしてまいりましたので、是非ご覧ください。 ・薪の取り出し方問題 二次燃焼の綺麗な炎を発生させながら高火力で炭を作る焚き火台、ということを基本コンセプトに考えて、設計・試作をしていく中で問題となったのは、炭の取り出し方です。 最初のプロトタイプなんかは、出来た炭を取り出すことは出来ても、危険な状態で取り出す状況となってしまいました。また本体のサイズを小さくすると、取り出せる炭の量は減ってしまうし、取り出しにくさに繋がってしまこともわかりました。 そこで、いかに綺麗に簡単に取り出せるか、ということがその後の課題として見えてきました。 安全性を考慮しながら利便性も追求することを考え、設計をしていきました。 火ばさみで一個一個を取って移動させるのも面倒だし、時間がかかるために炭の移動を開始してから、最後のほうは灰になってしまって、使い物にならない。そうすると料理するにも時間がかかってしまう。そうなると出来た炭を一発で料理をする場所、BBQコンロなどに移動させることができる方法となります。 現状モデルでは炭受けが引き出せる構造にすることで、炭の移動が出来るようにしておりますが、移動時の安全性をもっと確保できないかと現在も憂慮しております。 ・製品化に至るまでの工程 商品化に至るまでには、プロトタイプを3台製造しています。その都度問題点・課題を見つけ、設計から製造までを見直していきました。 プロトタイプ1号機 こちらに関しては、炎に関しては綺麗な二次燃焼も発生し、炎を楽しむという面では満足できる部分はあったのですが、炭の取り出しが非常にしにくい構造でした。 サイズも一番小さいモデルではあったので、実はソロキャンパーの娘は、自分がもし持っていくならこれ、ということも言っておりました。 プロトタイプ2号機 1号機の炭の取り出しにくさを解消すべく、サイズも少し大きくして、ロストルを取り出せるような構造体へ設計変更を行いました。 しかし実際に試験を行ってみると、高温による歪みによってロストルが安全に取り出すことが出来なくなってしまいました。取り出すことは出来ても安全性に欠けることとなってしまうので、再度この点が課題となりました。 また燃焼については、1号機はロストル部から壁内への吸気を行うための通気口を設けていたのですが、外部からの酸素の流入を増やすためにこちらをふさぎ、外部からの空気の取り込口を大きくしました。また壁内の厚みをより厚くし、二次燃焼口の数も減らすことで、壁内の密度を上げ勢いよく二次燃焼が発生するようにと考えたのですが、結果として1号機に比べて炎が不安定になってしまいました。 プロトタイプ3号機 3号機は炭の取り出しやすさを最優先事項として、構造を変更。ロストル部をスライド式で取り出しが可能な構造としました。こうすることで、炭を一度に取り出すことが可能とはなりました。 二次燃焼に関わる部分については、2号機と同じ構造としました。炎のことだけを考えると1号機が一番安定していたが、酸素の取り込みを考えるとあくまで外部のみのほうが二次燃焼は発生しやすいと考えました。どこに差があるのかを考えると、壁内の温度に差があるのはないかと考えていました。ただ、2号機に比べ安定性はロストル部の設計変更によるもので安定はしてきました。 当初の目標は最低限クリアしたことで、こちらをベースに商品化することとなりました。 ・今後の展望 商品化には至りましたが、まだまだ製品としては個人的には納得がいっていない部分があるので、今後もより良い商品としてお客様にお届けできるように改良はしていく予定です。 具体的には、炭の取り出し部分の改良。こちらはまだ使い勝手、安全性の部分で改良の余地は多く残っていると感じております。自らが使う立場になって考えてみて、こうだったら良いのという案は出ているのですが、まだ実用できるレベルには至っておりませんが、引き続き検証してまいります。 もうひとつは二次燃焼の安定化。こちらも使用環境にもよってしまう部分がもちろんあるのだけれども、より安定して二次燃焼が発生するように改良はしていきます。 プロトタイプでの検証を踏まえて、壁内の空気層の厚みの調整によって温度を上げることが出来ないかを考えています。 現状の商品でも今までには無いコンセプトの商品ではありますので、使用していただくお客様には満足いただけるとは考えておりますが、引き続き改良をしてまいりますので、次期の製品にもご期待いただければと思います。