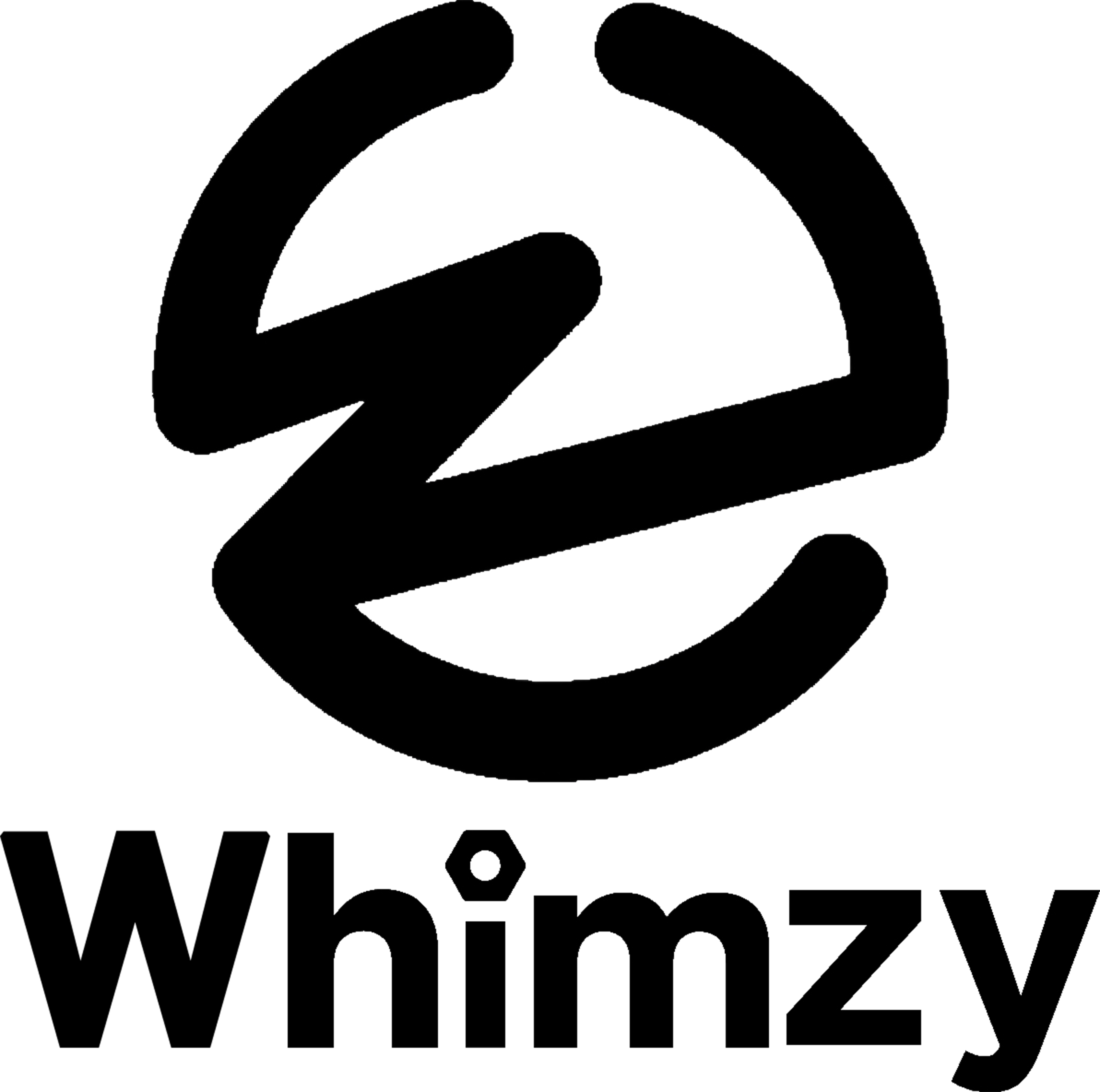2023/09/27 09:42
燃焼焚き火台 開発から商品化までのお話 Vol.2 前回から続きで、今回は具体的に商品開発に至るまでのことを、各ポイントに絞って開発者の大澤へのインタビューをしてまいりましたので、是非ご覧ください。 ・構造とサイズ 購入・準備した薪をキャンプ場で、焚き火台に合わせてまた薪を燃えやすくするためにバトニングをしたりすることはキャンプの醍醐味の一つではあると思うのですが、ファミリーキャンプで、お子様から「何か食べたい!」の要望が、火付けに時間が掛かると妻のご機嫌が・・・。一度は思い当たるところが有るのではないでしょうか?! そこで、一般的にキャンプ場やホームセンターで販売されている45㎝までの薪がそのまま投入可能であるサイズを前提としました。 また、強度面でもしっかりとしたものを作りたいというのは絶対条件であったため、それに見合う大きさという側面もあります。 やはり数回使って終わり、ということではなく、長く楽しんでもらう品物を作りたいという考えが根底にありました。 強度の面ではやはりコンパクトにする、軽量化する、となると使用する板の厚みを薄くしなければならず、そこを追究した場合には恐らく使用回数も、今までの板金経験上でたかが知れているものしか作れないのではないかと予想できました。 ですので、長く使用していただくための耐久性や火を使うことで発生する歪み等の影響、構造としては二次燃焼が発生するように、空気層を作るように二重構造として考えていたので、空気層の厚みをとるための間隔、それに対する板の厚みも考慮した上で、ギリギリのラインをついていけるように検証していきました。 ・薪と炭 前述したとおり、焚き火自体を楽しむということももちろんあるけれども、そのあとにBBQで炭を活用できるように、炭を取り出せる構造にしました。 現状市販されている二次燃焼焚き火台の多くが火を楽しむことに重点が置かれ、サイズ面でも大きな薪はもちろんそのままでは入らなかったり、ペレットでの使用前提のものであったりと、自分の考えるスタイルでは用途が限定されすぎて実用性には乏しいように感じており、自分が作るのであれば、これも出来るのではないか、ということはなるべく取り入れ行きたいと考えていました。 その中で、自分の中ではBBQも好きなので、薪で焚き火をした際に発生する炭を利用できないか、ということでした。もちろん二次燃焼焚き火台として薪を燃やして発生する炎でも調理は可能だけれども、料理の品目も限られてしまいます。一般的には炭を使ってのBBQのほうが幅は広がると考え、炭を有効活用できる形にする方向としました。 いくつか試作して試す中で、構造としては燃焼効率が高いために薪は非常によく燃えて、炭になるのは早かった。しかし炭の取り出し機能が無いと、どうしても炭が多くなってしまい、二次燃焼を起こすガスは多く発生しますがガスに引火する炎が炭による酸欠で消えてしまい、煙しか発生しない最悪な状況に陥りました。 そうなると炭を取り出しやすい構造にすることで、料理に活用することも出来て、より炎を楽しむことができると考え、設計に反映させ改良を重ねました。 ・二次燃焼 焚き火台を作るにあたっては、本来の実用性だけで考えれば、薪を燃やして炭になってそれを次の目的の料理に活用できれば、ということになり、単純に焚き火と考えた時には用途は関係がなくなる。 ただ炎がせっかく出るのであれば、二次燃焼の炎を見たい、それを楽しみたいと考えました。 ただただ単純に薪を燃やして炭が作れるというのであれば、一斗缶でも可能だったりするわけなので、そうではなくて焚き火を楽しむ、炎を楽しむ、ということを考えると二次燃焼が発生するような構造とする方向で形を考えていくことにしました。 またこのような構造とすることで、上記の炭を取り出すことを考えても燃焼効率が高くなるために、プラスに働いているのではないかと考えております。 ただ、現状販売しているモデルもまだまだ改良の余地があるとは感じているので、引き続き検証を重ねて、より安定して綺麗な炎が見られるようにモデルのバージョンアップは考えています。